箕面市 > 子育て・教育・文化 > 教育 > 箕面市教員養成セミナー「ぴあ・カレッジ」 > R7「ぴあ・カレッジ」第7回セミナーの様子
更新日:2025年9月29日
ここから本文です。
令和7年度「ぴあ・カレッジ」第7回セミナーの様子
令和7年(2025年)8月30日(土)に今年度の「ぴあ・カレッジ」の第7回目のセミナーを箕面市役所で実施しました。
第7回目のセミナーは、
1.「ともに学び ともに育つ」箕面市の支援教育について理解を深めること
2.「人権」「人権教育」について知り、考えること をめあてとしました。

セミナーの前半は、箕面市教育委員会人権施策室の脇指導員より「支援教育について」の講義を受けました。
通常学級や通級指導教室の利用、支援学級の学びの場の違いを知りました。そして、合理的配慮や個別の支援、授業のユニバーサルデザイン、SWPBS(スクールワイドポジティブ行動支援)など大切にしていきたいことを学ぶことができました。
障がいのある子どもと周りの子どもたちが集団の中で一人ひとりを尊重し、ちがいを認めあうことやすべての子どもたちが安心で楽しい学校生活を過ごすことができるように支援していくことの大切さを改めて感じる時間となりました。

セミナーの後半は、箕面市教育委員会人権施策室の山北指導主事より「人権教育について」の講義を受けました。
「人権」とは、すべての人が生まれながらに持っている権利であり、一人ひとりがかけがえのない存在であること、学校生活のあらゆる場面で「人権教育」を行っていくことを改めて学びました。
さまざまな人権課題やマジョリティ特権、マイクロアグレッションなど実態を知ることができました。すべての子どもたちが安心して過ごすことができる学級や居場所づくりの重要性に気付くとともに子どもたちの言葉や行動の背景を見取っていくことの大切さを学びました。


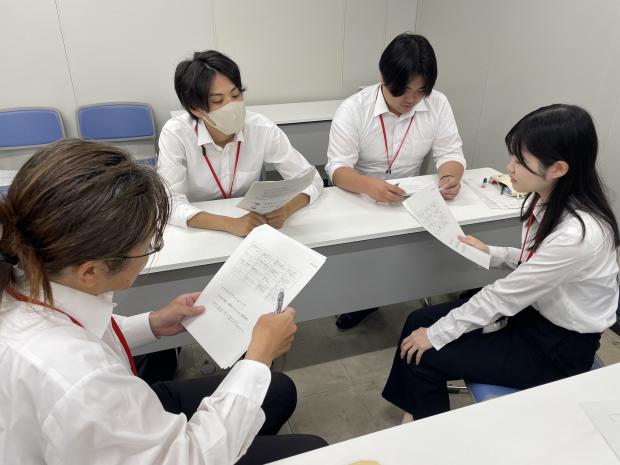
【ぴあ・カレッジノート(受講生のふりかえり)より】
<学んだこと・今後に生かしていきたいこと>
・支援は特別ではなく、みんな等しく受けるものであり、「特別支援教育」ではなく「支援教育」であることを知った。
・支援教育と聞いて、支援学級や通級、合理的配慮ばかりに注目していたが、まずは一人ひとりの子どもに応じた環境を整えることが大切だと学んだ。
・マイクロアグレッションについて、マジョリティ側だと気付くことが難しいと思う。だからこそ意識的に自分や他の人の言葉を一度立ち止まって考えていく必要性を感じた。
・「自分らしく生きる」ということは教育現場だけではなく、社会でもよく耳にするようになった。自分らしく生きることを追求しすぎては、誰かの自分らしくを壊してしまうかもしれない。みんなが自分らしくいるためには、「わたしOK、あなたOK」を考え続けなければならないし、考えた先に過ごしやすい社会が存在すると思う。
<感想>
・支援教育は、すべての子どもたちのためにあり、みんなが安心・安全で過ごしやすい環境を教師としてつくっていく必要があることを学んだ。
・マジョリティ特権という言葉が印象的だった。自分自身が普段何不自由なく過ごせていることが「当たり前」ではなく、異なる背景や事情を抱えている人たちがいることを忘れずに考えていかなければならないと感じた。全体を通じて、「差別」を減らすためには、学校全体で指導方法やなどは統一することが大切であると感じた。
・「教師は差別をなくすことができる仕事」という言葉が非常に印象に残った。少し先の未来をつくり、未来を担っていく存在である子どもたちとの向き合いかたや関わりかたの一つひとつに責任を持っていきたい。
よくあるご質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください



