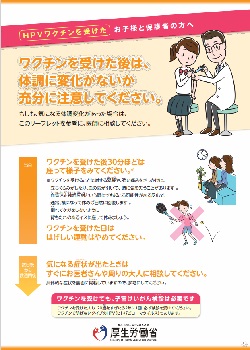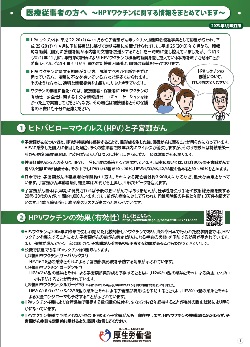ここから本文です。
子宮頸がん予防ワクチン
子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス感染症)ワクチンについて
- 子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、平成25年(2013年)4月1日より定期予防接種として実施しています。その後、平成25年6月に国から積極的な接種勧奨を差し控えるよう通知が出されていましたが、令和3年11月にその通知が撤回されたことを受けて、令和4年4月から個別通知による接種勧奨を再開しました。
- HPVワクチンを含む、子どものA類疾病の定期接種は、努力義務であり、強制ではありません。接種にあたっては、かかりつけの医師と相談し、ワクチンの有効性とリスクについて保護者及び接種するご本人が十分に理解したたうえで接種を受けるようお願いいたします。
- なお、定期接種対象年齢のかたで接種を希望されるかたは、定期予防接種医療機関で無料で予防接種を受けることができます。
- 予診票については、中学1年生のかたを対象に箕面市から一斉発送します。発送時期については、もみじだよりにてお知らせしています。一斉発送のタイミングよりも早く接種を希望されるかたは、子どもすこやか室にお電話ください。
- HPVワクチンを接種希望で、予診票を紛失されたかた、または箕面市に転入されたかたは、こちら( 外部サイトへリンク )から予診票の発行手続きができます。
ホームページ・リーフレット(厚生労働省作成)
ホームページ(厚生労働省)
リーフレット(厚生労働省)
接種を検討されるかた向け(画像をタップまたはクリックしてください)
- 概要版
- 詳細版
- 接種を受けた後
医療従事者のかた向け(画像をタップまたはクリックしてください)
- HPVワクチンに関する情報をまとめています。
9価HPVワクチン接種について
ホームページ(厚生労働省)
- 9価HPVワクチン接種のお知らせ ( 外部サイトへリンク )
子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)について
- 子宮頸がんとは、女性の子宮の入り口(頸部)にできるがんのことです。
- 自覚症状はほとんどありませんが、進行すると茶色のおりものや月経に関係のない出血、下腹部の痛み、性行為の際の出血などの症状が現れます。
- 子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスが原因で発症します。
- HPVには多くの種類がありますが、このうち15種類が子宮頸がんのハイリスクに分類されています。すべてのHPVの感染を防ぐものではありませんが、シルガード9は16型・18型に加え、ほかの5種類のHPVの感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。サーバリックスおよびガーダシルは、子宮頸がんの原因の約50~70%を占める16型・18型の2種類のウイルス感染を予防します。
- HPVに感染しても、多くの場合は自然に検出されなくなりますが、一部が数年~十数年間かけて前がん病変の状態を経て子宮頸がんを発症します。
- 日本では毎年、1.1万人の女性が子宮頸がんにかかり、約2,900人の女性が子宮頸がんで亡くなっています。
- 日本では、40歳までの女性の癌による死亡の第2位は、子宮頸がんによるものです。
- ワクチンでHPV感染を防ぐとともに、20歳になったら子宮頸がん検診を定期的に受診しましょう。
箕面市では20歳から子宮頸がん検診を毎年、無料で受けることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
接種対象年齢及び回数
- 対象年齢:小学校6年生から高校1年相当年齢の女性
(標準的な接種期間は中学1年生)
| 接種間隔 | 2回目 | 3回目 | |
| サーバリックス(2価) |
標準:1回目から1か月 (1回目から1か月以上) |
標準:1回目から6か月以上 (1回目から5か月以上、 |
|
| ガーダシル(4価) | 標準:1回目から2か月 (1回目から1か月以上) |
標準:1回目から6か月以上 (2回目から3か月以上) |
|
|
シルガード9 (9価) |
1回目を15歳未満で接種 | 標準:1回目から6か月 (1回目から5か月以上) |
2回で終了(※) |
| 1回目を15歳以上で接種 | 標準:1回目から2か月 (1回目から1か月以上) |
標準:1回目から6か月以上 (2回目から3か月以上) |
|
- (※)合計2回の接種が完了できる方は、1回目の接種を小学校6年生の年度から15歳の誕生日の前日までに受け、その後5か月以上あけて2回目の接種を受けた方です。2回目の接種が5か月未満の場合は、3か月以上あけて3回目の接種が必要になります。
- 間隔の〇ヶ月という表記は、1か月の場合、翌月の接種日同日以降に接種します。
例:間隔2か月以上…接種日9月15日の場合、次回は11月15日以降です。
交互接種について
- 原則、3回とも同一のワクチンで接種を完了してください。
- 2価HPVワクチン(サーバリックス)や4価HPVワクチン(ガーダシル)で規定の回数の一部を完了し、9価HPVワクチンで残りの回数の接種を行う“交互接種”についても、実施して差し支えないとされています。
- 交互接種の有無にかかわらず、かかりつけ医等から、ワクチンの有効性と接種による副反応が起こるリスク等について説明を受け、ご理解いただいた上で接種を行ってください。
- なお、交互接種を行う場合の接種間隔は、9価HPVワクチンの接種方法に合わせてください。
- 妊娠中もしくは妊娠している可能性がある場合は原則接種できません。
接種方法
- 接種の際は母子健康手帳を忘れずに持参してください。
- 2価、4価のみが記載された予診票を使用し、9価も選択いただけます。お手元に予診票があるかたはご利用ください。
- 接種の際は保護者の同伴が望ましいですが、やむを得ず同伴できない場合は、接種するお子様が13歳以上であり、保護者が事前に説明文を十分に理解し、予診票に署名することで、同伴しなくても接種することができます。
- 定期予防接種は個別接種となりますので、定期予防接種医療機関でご予約のうえ接種してください。
- HPVワクチンは、接種部位に強い痛みが生じやすいワクチンです。かかりつけ医での接種をお勧めします。
接種費用
無 料
※ただし、対象年齢(小学校6年から高校1年相当年齢まで)に当てはまらない場合や接種間隔が異なる場合(1回目→2回目を1週間の間隔で接種してしまったなど)は任意接種となり、有料となります。
※任意接種の場合、健康被害が生じた場合に予防接種法に基づく補償を受けることができませんのでご注意ください。
ワクチンの種類
不活化ワクチン
留意事項
- 予防接種は、体調の良い日に行ってください。
- 予防接種を受ける予定でも、体調が悪い場合は、かかりつけ医とよく相談して接種の判断をしてください。
※37.5度以上の明らかな発熱がある場合は接種できません。 - 接種後30分程度は、急な副反応が出た場合に備え、医療機関で背もたれのある椅子に座って休み、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
- 接種後1週間は副反応の出現に注意し、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。また、当日は激しい運動は避けましょう。
- 母子健康手帳は、予防接種を受けた大切な記録です。接種歴の確認のためにも大切に保管してください。
副反応について
- HPVワクチン接種後の主な副反応としては、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などがあげられます。
- また、ワクチン接種後に見られる副反応について、国は接種との因果関係を問わず報告を収集しており、定期的に専門家が分析・評価しています。その中には、稀にアナフィラキシー、ギラン・バレー症候群、急性散在性脳脊髄炎 (ADEM)、複合性局所疼痛症候群 (CRPS)などの重い副反応の報告もあります。
- 重い副反応がなくても、気になる症状や体調の変化がみられた場合は、接種をうけた医師にご相談ください。
- 予防接種によって健康被害(入院が必要な程度の障害など)が生じ、それが予防接種によるものであると認定された場合、予防接種法に基づく補償を受けることができる健康被害救済制度があります。
- 予防接種の効果・副反応などを理解した上で接種してください。HPVワクチンは合計3回接種しますが、1回目、2回目の接種で気にかかる症状が現れたら、それ以降の接種を中止することができます。
- 気になることがある場合は、接種を受けた医療機関、かかりつけの医師などにご相談ください。
関係リンク
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください