ここから本文です。
2.土地利用
市街化区域と市街化調整区域
都市計画区域を優先的かつ計画的に市街化すべき区域(市街化区域)と、当面できるだけ市街化を抑制すべき区域(市街化調整区域)に区分して、無秩序な市街地の拡大を防止し良好な市街地の整備・保全をはかる制度を市街化区域と市街化調整区域の区域区分(線引き)と言います。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に計画的・優先的に整備をはかる区域で、道路・公園・下水道などの整備を積極的に推進するほか、民間の開発行為も一定の基準にかなったものは許可されることになっています。
一方、市街化調整区域は都市間を結ぶ道路などの整備は別として、市街化を促進するような整備は原則として行うことができません。
箕面市では、昭和45年6月20日市街化区域と市街化調整区域の線引きの決定を行い、その後市街化の進展に伴い段階的に市街化区域を見直し現在に至っています。
【箕面市の市街化区域(左)と市街化調整区域(右)】


用途地域
用途地域は、都市における土地利用の計画を実現していくための規制、誘導という役割を果たすもので、建物の用途や形態別に12種類の地域に細分されます。
箕面市では、住環境の維持向上とまちの活性化に重点をおき、住居系と商業系の9種類の地域を指定しています。
【箕面市における9種類の用途地域】
第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。

第二種低層住居専用地域
主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
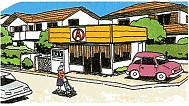
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。
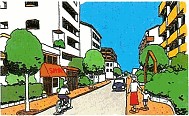
第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
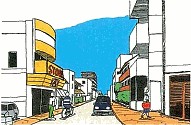
第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
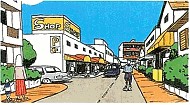
準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

近隣商業地域
近隣の住民が日用品の買い物をする店舗などの業務の利便の増進をはかる地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
商業地域
映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進をはかる地域です、住宅や小規模の工場も建てられます。
特別用途地区
特別用途地区は、用途地域内において特別の目的から土地利用の増進、環境の保護などをはかるために定める地区で、当該用途地域の指定を補完するものです。
箕面市では、以下の3地区が指定されています。
特別業務地区
卸売業に供する店舗、事務所などが集中立地している地区の環境を保護するため、コム・アート・ヒル(船場地区)の商業地域を特別業務地区に指定しています。
この地区では、箕面市特別業務地区建築条例により、風俗営業、ぱちんこ屋などの制限を付加して用途地域を補完しています。
- 箕面市特別業務地区建築条例(平成29年10月11日改正)は箕面市例規集(外部サイトへリンク)によりご確認ください。
特別業務地区内における建築制限について(平成29年10月11日改正)
特別業務地区の区域(地区計画(当該地区計画の区域の面積が三ヘクタール以上のものに限る。)が定められている区域内において、建築基準法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で建築物の用途の制限が定められている区域を除く。)では、建築基準法第四十八条第十項に規定するもののほか、次に掲げる建築物は建築できません。
一 箕面市ラブホテル建築の規制に関する条例(昭和五十八年箕面市条例第二十九号)第二条第二号に規定するラブホテル
二 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
三 建築基準法別表第二(り)項第二号に係るもの
四 ぱちんこ屋
五 風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第五号に係るもの
六 風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係るもの
七 ボーリング場
八 住宅及び共同住宅(事務所、卸売店舗その他これらに類する用途を含むもののうち規則(※)で定めるものを除く。)
九 畜舎(床面積の合計が十五平方メートル以下のものを除く。)
(※)規則で定めるもの
1 住宅 住宅部分の全てを当該建築物の三階以上の階に配置するもの
2 共同住宅 住戸又は住室部分の全てを当該建築物の三階以上の階に配置するもの
箕面森町広域誘致施設地区
交通利便性の高い立地条件やすぐれた環境を活かし、広域を対象とする商業施設などの立地をはかるため、箕面森町(水と緑の健康都市)のうち商業地域を箕面森町広域誘致施設地区に指定しています。
この地区では、箕面森町広域誘致施設地区における建築物の制限等に関する条例により、商業施設の機能の充実に必要な用途の緩和や地区に相応しくない建築物の用途の制限をすることで用途地域を補完しています。
- 箕面森町広域誘致施設地区における建築物の制限等に関する条例(平成27年6月25日)は箕面市例規集(外部サイトへリンク)によりご確認ください。
箕面森町広域誘致施設地区における建築制限などについて(平成27年6月25日制定)
箕面森町広域誘致施設地区内においては、建築基準法第四十八条第十項に規定するもののほか、次に掲げる建築物は建築できません。
一 住宅
二 兼用住宅
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
五 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)
六 病院
七 ホテル又は旅館
八 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの
九 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十 個室付浴場業に係る公衆浴場及び建築基準法施行令第百三十条の九の五に定めるもの
また、北部大阪都市計画水と緑の健康都市地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例により、住宅宿泊事業法第二条第五項の届出住宅(以下「届出住宅」という)についても建築できません。
なお、建築物が耐火建築物又は準耐火建築物である場合は、次のとおり制限を緩和しています。
一 原動機を使用する工場について、作業場の床面積の上限(合計150平方メートルまで)を撤廃
二 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物について、火薬類以外の取扱量を緩和(詳細は条例参照)
居住環境保全地区
住民の安全で快適な生活の確保のため、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」の全ての地域を居住環境保全地区に指定しています。
この地区では、箕面市居住環境保全地区における建築物の制限に関する条例により、住宅都市として良好な居住環境を保護する地域においては民泊ができないように用途地域を補完しています。
- 箕面市居住環境保全地区における建築物の制限に関する条例(令和元年6月26日)は箕面市例規集(外部サイトへリンク)によりご確認ください。
居住環境保全地区内における建築制限について(令和元年6月26日制定)
居住環境保全地区内においては、建築基準法第四十八条第一項から五項までに定めるものを除くほか、住宅宿泊事業法第二条第五項の届出住宅は建築できません。(ただし、第一種住居地域において、届出住宅の用に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以下の場合を除く)。
高度地区
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を保護する等のために、建物の高さの最高限度または最低限度を定めるものです。
箕面市では、独自に第1種から第8種の高度地区を指定し日照、採光、通風など居住環境の保護に努めています。
高度利用地区
高度利用地区は、用途地域内において都市空間を有効に利用し、土地の合理的な高度利用と都市機能の増進をはかるために、建築面積の最低限度、建ぺい率の最高限度、容積率の最高・最低限度などを定めるものです。
箕面市では、箕面駅前地区をはじめとして、3地区を高度利用地区に指定しています。
防火・準防火地域
防火地域・準防火地域は、市街地において建築物の耐火性能を向上させることにより、火災による危険を軽減させるものです。このため建築物の密集した火災危険率の高い地域に指定されます。
箕面市では、主として商業地域を防火地域に、近隣商業地域を準防火地域に指定しています。
風致地区
風致地区では、都市における自然の風致や景観を維持育成し、自然美豊かな景観を保護するために定めるものです。
箕面市では、大阪府営箕面公園を中心に指定しており、府条例によって建築物や工作物の位置、形態などに制限が加えられ、周辺の風致との調和を図っています。
生産緑地地区
生産緑地地区は、市街化区域内の農地などの緑地機能に着目して、公害や災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地などを保全し、良好な都市環境の創出をはかるものです。
促進区域
促進区域は、関係権利者に対して都市計画に沿って土地の積極的な利用努力を義務づけることができる区域です。
箕面市では、土地区画整理促進区域や住宅街区整備促進区域などがあります。
地区計画
地区計画は、都市全体を対象とする都市計画による統一的・標準的な規制に加え、各地区の特性に応じ、地区レベルで建築物の用途・形態などに関する制限をきめ細かく定めるとともに、地区の道路・公園などについて一体的に計画しそれぞれの地区にふさわしい良好な市街地の整備、保全をはかるものです。
地区計画で決めることのできる項目
地区の整備方針、特性に応じ次の項目のうち必要なものを定めることができます。
- 地区内の道路、公園、緑地、広場その他の公共空地の配置及び規模
- 建築物などの制限
- 建築物などの用途・高さの最高限度、最低限度
- 建築物の容積率の最高限度又は最低限度
- 建築物の建ぺい率の最高限度
- 建築物の敷地面積や建築面積の最低限度
- 壁面の位置の制限 など
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください



