
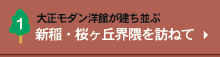
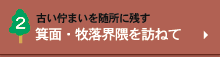
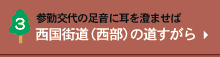
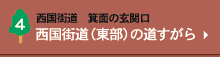
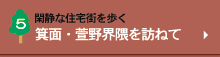
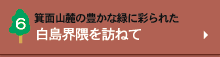
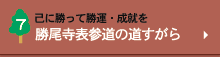
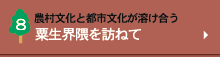
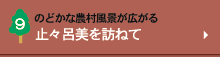
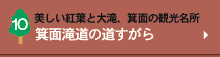

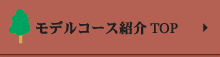 |
 |
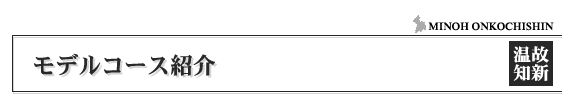
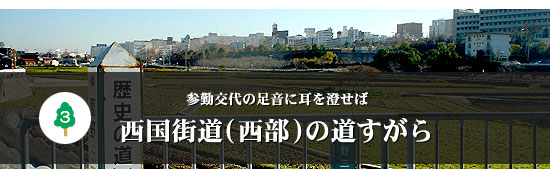

箕面の市街地を東西に横断する西国街道。
京都から神戸へと向かう国道171号に、沿うように走っています。今も昔も変わらぬ交通の往来に、時の参勤交代の行列が重なります。 |
 |
![西国街道西部コース[所用時間180分]](img/time03.gif) |
![モデルコース紹介[3] Map](img/map03.gif)
1. 瀬川神社 2. 弁慶の鏡水 3. 願正寺 4. 坪 5. 瀬川・半町本陣跡 6. 牛まわしの塔 7. 一番通りと保護樹木 8. 教学寺
西国街道
箕面地方は日本の中心であった京都と朝鮮半島との玄関口であった九州の大宰府を結ぶ要衝に位置しており、これを横断する山陽道は、戦国時代にはとても重要な軍用道路として人馬が頻繁に往来していました。江戸時代に入ると山陽道は「西国街道」と呼ばれるようになり、京−西宮間の16里は「山崎街道・山崎通」とも呼ばれていました。 西国街道は京から山崎を経て摂津国に入り、芥川(高槻市)・郡山(茨木市)から箕面市域の南部を通過し、瀬川から南下して昆陽(伊丹市)・西宮(西宮市)に至り、さらに西国へと通じています。
寛永12年(1635)武家諸法度で大名の参勤交代が制度化されてからは、兵庫・西宮から京・大津への近道として西国諸大名の大名行列が次第に通行するようになりました。江戸時代中期以降においては、あたかも参勤交代のために造られた道かのように大名行列がこぞって西国街道を利用するようになり、街道沿いの駅所に大変な混乱を招きました。そして安永4年(1775)、ついに幕府は中国・四国・九州の諸大名になるべく本街道(大阪回り)を通行するように指示し、さらに翌年の安永5年(1776)には、特に天皇や君主に許可を得た者以外の参勤交代の際の通行を禁止しました。しかしそれにもかかわらず、なおも西国街道は参勤交代で利用され続けたということです。 |
|

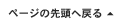
 |
|
|
|