
|
 |
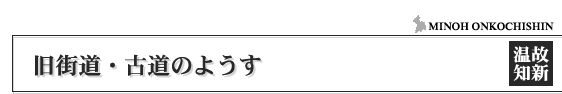
箕面を通る旧街道・古道の様子箕面の歴史は丘陵や山地のふもとからはじまります。市域の南部に広がる千里丘陵の西端、瀬川地区からは縄文時代の土器や石器が発見され、数千年のむかしに人々がこの地区で生活したことが知られます。萱野の北、如意谷の山中からは銅鐸が出土し、この近辺に弥生時代の人が生活していたことをうかがわせます。
中近世の箕面は、西国街道を行き交う人々や、西国二十三番札所である勝尾寺、役行者ゆかりの瀧安寺などを参拝する人々で賑わい、それにともなって様々な道が設置されました。
近年になってようやく、旧街道や古道が「歴史の道」として評価され見直されるようになりました。
この箕面には、十数の道が通っていたといわれています。
そのうちのいくつかをご紹介します。
西国街道
西国街道は古代、山陽道とよばれ、京の羅城門から九州の太宰府に至る大路で、現在の箕面市には草野駅(かやののうまや)、豊嶋牧(てしまのまき)が設けられていました。中世になると瀬川は宿場となり、京と西国を結ぶ近道として賑わう重要な道になります。
勝尾寺表参道
勝尾寺への参道は幾筋もありますが、西国街道に面して建つ粟生新家の大鳥居からまっすぐ北へ、粟生外院の帝釈寺の横を過ぎ、府道箕面池田線を横切り山へ入って行く道が表参道です。
箕面街道
西国街道を牧落の高札場跡で南北に横切っているのが箕面街道で、大坂(阪)から箕面寺(瀧安寺)への最短距離の道でした。
|
|

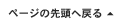
 |
|
|
|