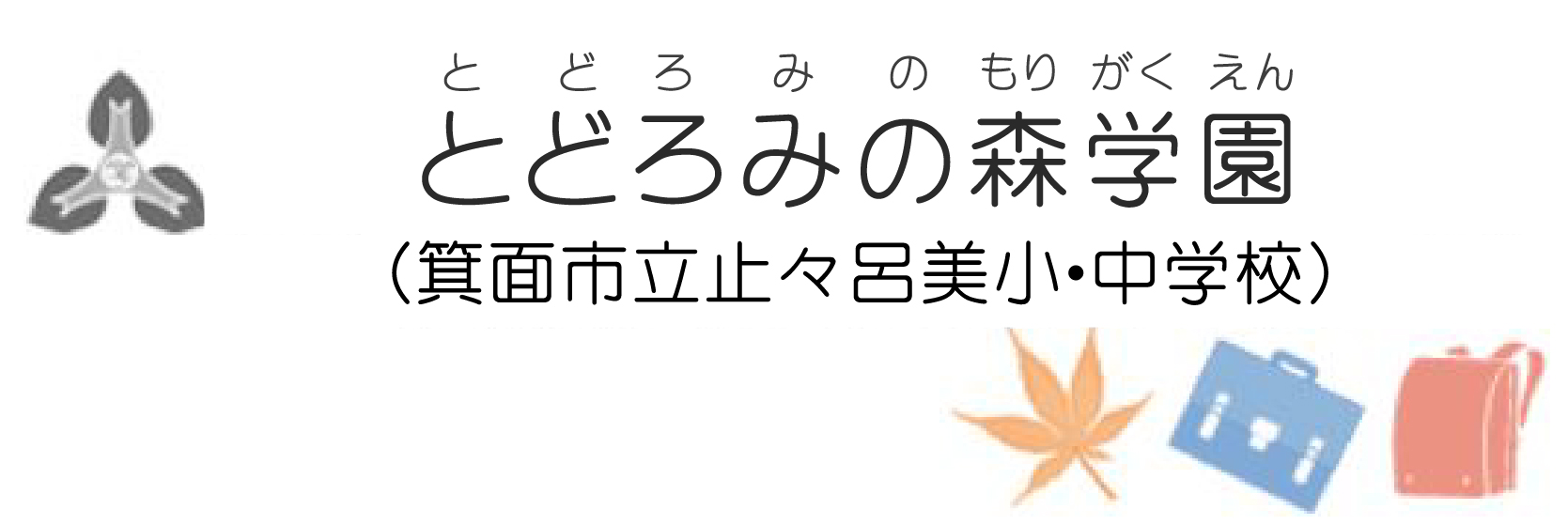ここから本文です。
とどろみの森学園(箕面市立止々呂美小・中学校) > とどろみの森学園の教育目標について
更新日:2025年5月7日
とどろみの森学園の教育目標について
とどろみの森学園は、公立学校では大阪府で最初の施設一体型小中一貫校として開校しました。
児童生徒数は、約1200名となり(令和7年4月1日現在)、開校以来、小中一貫教育の推進を学校教育の柱として進めています。

教育目標
学ぶ力、認め合う心、輝く未来を創造する学校
めざす子どもの姿
(1)自ら課題を見つけるとともに、未知のことにも挑戦できる「確かな学力」と「体力」を身につけた子ども
(2)多様性を認め、相手を思いやり、異なった考えや文化を持つ仲間とともに活動できる子ども
(3)夢や志を持ち、自らの判断により、社会に参画し、貢献できる子ども
めざす学校の姿
(1)清潔で、規律があり、安全で、安心して学べる学校
(2)「子ども」、「教職員」、「保護者」、「地域」が相互に信頼の「絆」で結ばれた学校
(3)「子ども」、「教職員」、「保護者」、「地域」がそれぞれに「幸せ(well-being)」を感じられる学校
学校いじめ防止基本方針
本校では、学校いじめ防止基本方針を定め、いじめのない学校づくりを目指しています。上のリンクをクリックするとご覧いただけます。
研究テーマ
【2025年度研究テーマ】
子どもが主体感をもてる授業づくり ~ キーワードは自己調整 知るからやってみるへ~
【研究仮説】
▶主体的に学ぶとは? ”主体的に学ぶ”をどう捉えるか?
「主体的」とは、「意欲的」「積極的」とはちがい、単に自ら行動するだけではなく、学習の結果を受け止め「次にどうするか?」と考え、行動を調整していく姿勢を指します。自己選択・自己決定で"知る"や"やってみる"という学習に取り組み、自己調整を進めることこそが、主体的に学んでいる姿、つまり子どもが主体者と言えるのです。
▶自己調整の要素がある学習
自己調整しながら学習を進めるとは、与えられた学習課題に対して、自分なりの目標や計画を立てることです。これは、単に「これをしなさい」という指示を待つのではなく、「まずこれからやってみよう」と自ら判断し、行動に移す主体的な姿勢を意味します。このとき、学習方法を自分で選択できると、より主体的に学びに関わることができ、次の学習へのモチベーションも高まります。
学習を実行した後は、自分の行動や選択した方法について振り返ります。特に、学習内容そのものではなく、「どのように学習したか」という行動や方法に着目すると、次の学習に向けた改善点を見つけやすくなります。また、振り返る前に学習の成果を確認するステップを設けることで、自分の選択や行動が適切だったかを客観的に判断しやすくなります。こうして、「次はこうしたい!」という意志が生まれ、さらに主体的な学びへとつながっていくのです。

5周年記念航空写真

中庭